
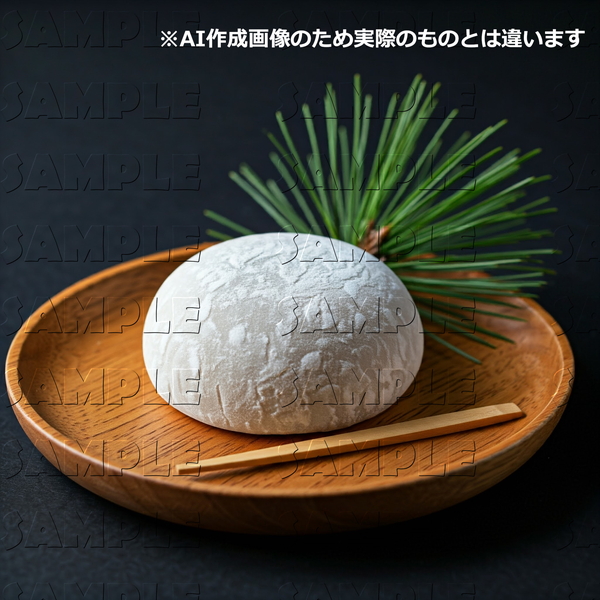



















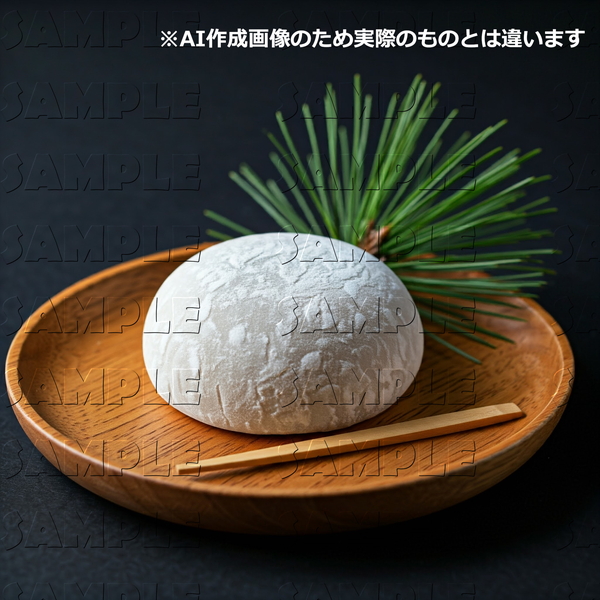




























3,651 件中 2,751~2,800件 を表示

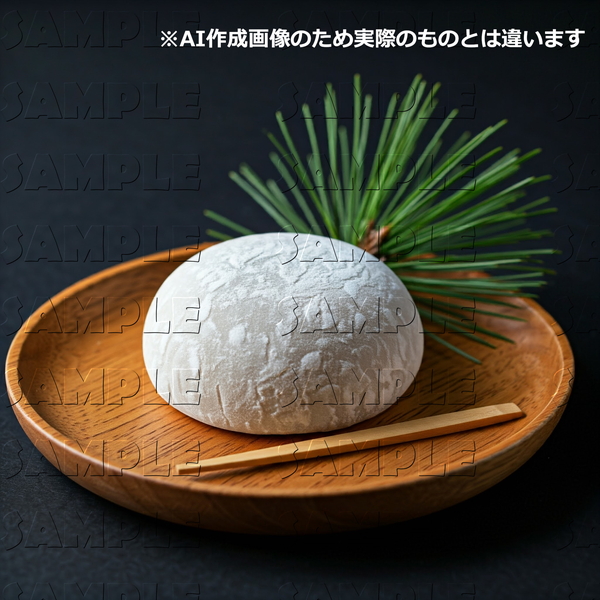



















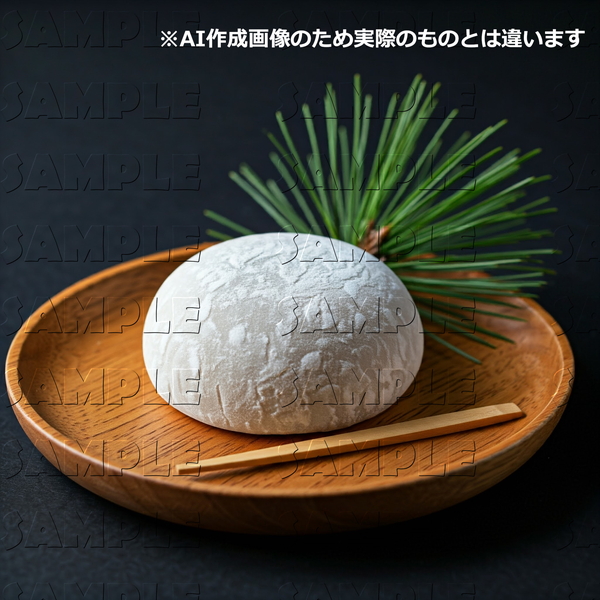




























3,651 件中 2,751~2,800件 を表示